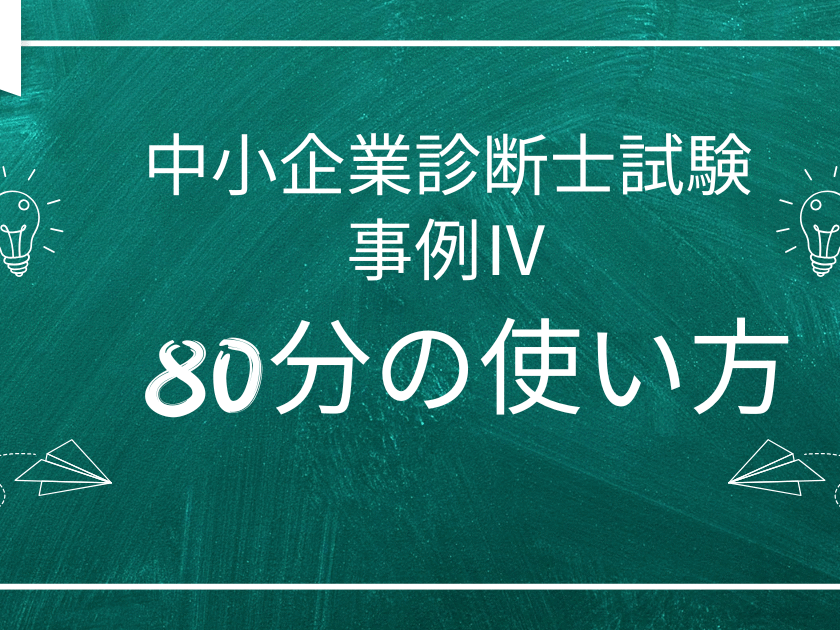
中小企業診断士試験 事例Ⅳ|80分の使い方を徹底解説!得点源に変える時間配分戦略とは?
中小企業診断士試験のなかでも、多くの受験生が苦戦するのが「事例Ⅳ」。財務・会計を中心としたこの科目は、文系の受験生にとって特にハードルが高く感じられがちです。
しかし実は、事例Ⅳこそ最も努力が得点に直結する科目。型を覚え、パターンを習得し、時間配分の戦略を確立すれば、「苦手」から「得点源」へと大きく変貌を遂げることが可能です。
この記事では、80分という限られた試験時間の中で、いかに得点を最大化するかという視点から、実際の試験戦略や勉強方法までを体系的に解説していきます。
目次
- 事例Ⅳは「諦め科目」ではなく「努力型得点源」
- 合格に必要な事例Ⅳの戦略と戦術
- 【図解あり】80分の理想的な使い方
- 【実録】R6年度の実際の時間配分と反省点
- 事例Ⅳに強くなる3つの学習施策
- まとめ:合格の鍵は「配分」「準備」「執念」
1. 事例Ⅳは「諦め科目」ではなく「努力型得点源」
「計算が苦手だから…」「理系じゃないから…」そんな理由で事例Ⅳを“捨て科目”にしていませんか?
それは大きな誤解です。事例Ⅳは、出題される論点がある程度パターン化されており、正しい準備をすれば安定して得点できる非常に「攻略しやすい」科目です。
- 毎年出題されるCVP、NPV、経営分析などの定番問題
- 暗記によって再現性が高い解法を習得可能
- 記述やアイデアが求められる事例Ⅰ〜Ⅲより、点数のブレが小さい
つまり、自分の努力で得点をコントロールしやすい唯一の事例とも言えます。
2. 合格に必要な事例Ⅳの戦略と戦術
戦略:60点以上を確実に
事例Ⅳの目標はズバリ「60点以上を安定して取る」こと。事例Ⅰ〜Ⅲでの点数が伸び悩んでも、事例Ⅳでの得点で合否が大きく左右されます。
戦術:時間配分がすべて
80分という制限時間内に、全ての設問に手を付けるためには、あらかじめ時間配分を決めておくことが極めて重要です。各設問にかける時間の目安と、優先順位を持って取り組むことで、ミスのリカバリーも可能になります。
- 経営分析・文章問題:型に沿って素早く回答
- CVP・セールスミックス:基礎問題で確実に得点
- NPV:時間がかかるが配点が高い、最後まで粘る
3. 【図解あり】80分の理想的な使い方
以下が理想的な時間配分モデルです。
| セクション | 時間目安 | 指針 |
|---|---|---|
| 段取り・全体把握 | 5分 | 設問構成を確認し戦略を決める |
| 経営分析 | 10分 | パターン通り、スピード重視 |
| 文章問題 | 10分 | 解答の型を活用し速攻で処理 |
| CVP・その他 | 20分+α | 確実に得点。凡ミス注意 |
| NPV | 20分+α | 時間がかかるが高配点。手を抜かない |
| 検算 | 10分 | 計算ミスのチェック。1〜2点を拾いに行く |
4. 【実録】R6年度の実際の時間配分と反省点
理想通りに行けば良いのですが、本番では想定外の事態が起こります。以下は令和6年度の実際の時間配分例です。
- 段取り(5分):問題全体を俯瞰して解く順を決定
- 経営分析・文章(20分):ここは予定通り処理
- セールスミックス(10分):計算にやや詰まる
- NPV①〜②(25分):時間が足りず途中で切り上げ、部分点狙いへ変更
- 検算(5分):全体の整合性を確認しながら、死ぬ気で記入
ポイントは、「途中で軌道修正しながらも空欄を作らない」こと。部分点をかき集める粘り強さが求められます。
5. 事例Ⅳに強くなる3つの学習施策
①段取り練習を徹底する
模試や過去問演習では必ず80分の制限時間を設け、段取りと時間感覚を体に叩き込みましょう。
②暗記で解法を自動化する
CVP、NPVなどは「考えずに手が動く状態」が理想。使う公式、設問パターン、回答フォーマットを完全に身体に染み込ませます。
③事例Ⅳの勉強時間を最優先にする
苦手な科目ほど、早めに着手し、毎日少しずつでも触れ続けることが重要です。後回しにすると「いつまでも苦手」なままです。
6. まとめ:合格の鍵は「配分」「準備」「執念」
事例Ⅳは、他の事例と違い、「知識」よりも「処理力と鍛錬」が求められる科目です。
その中で勝ち抜くためには、
- ① 時間配分という武器
- ② 解法を反復して身体に染み込ませる準備
- ③ 本番であきらめない執念
この3つがカギを握ります。
あなたも今日から「80分の使い方」を意識した学習を始めてみてください。それが合格への最短ルートになるはずです。
