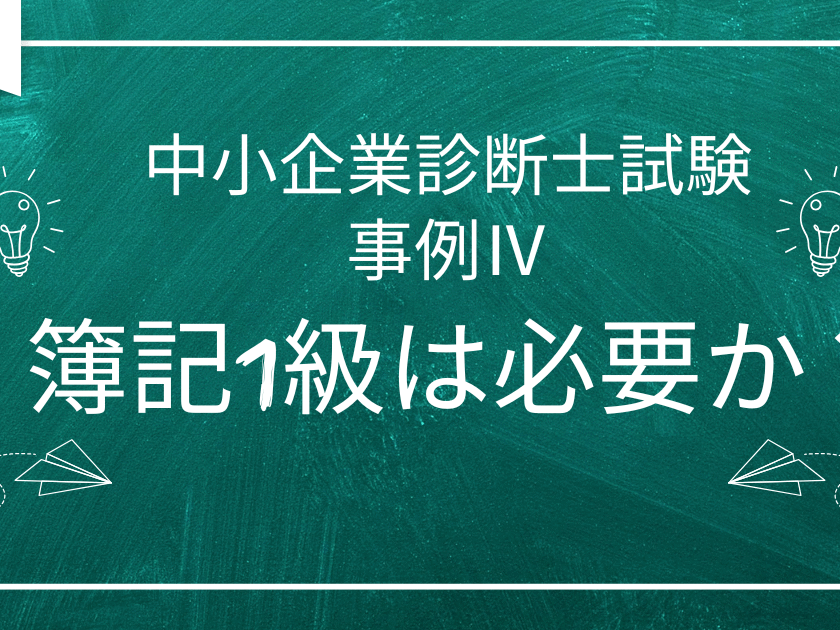
「事例IVが不安だから、簿記1級を始めようと思います」
この言葉、何度聞いたことでしょうか。
中小企業診断士試験の受験生にとって《事例IV=財務・会計》は鬼門。
だからこそ、「簿記1級で事例IVに備えよう」と考える人が少なくありません。
しかし、私はその選択に明確に否定的です。
なぜなら、それは「遠回りどころか、合格から遠ざかる」危険な戦略だからです。
簿記1級と診断士・事例IVは似て非なる試験
まず、両者の違いを明確にしておきましょう。
| 観点 | 簿記1級 | 診断士試験・事例IV |
|---|---|---|
| 目的 | 会計の専門家を育てる | 経営判断のできる実務家を育てる |
| 試験形式 | 純粋な会計処理・理論の正確性を問う | 計算+判断+記述による“意思決定力”を問う |
| 難しさの本質 | 幅広い論点と深い会計知識 | 時間制限下での判断力と処理スピード |
| 合格率 | 10%未満(超高難度) | 合格には限られた論点の“型”と“戦略”が重要 |
つまり、簿記1級は“正確な会計処理を行う専門家”の資格であって、
診断士試験・事例IVのような“経営者に助言する意思決定者”の訓練とはまったく性質が異なります。
なぜ、受験生は簿記1級に走ってしまうのか?
主な理由は「不安」と「安心感の追求」にあります。
- 「数字が苦手だから基礎からやり直したい」
- 「点数が安定しないから、簿記1級で力をつけたい」
- 「勉強している実感があるから安心できる」
しかしこの考え方は、まさに“資格勉強が目的化してしまった状態”です。
その結果、合格に必要な実戦力の鍛錬が後回しになってしまうのです。
合格に必要なのは「処理力」ではなく「対応力」
診断士2次試験の事例IVで本当に求められているのは、
- 制限時間内での優先順位付け
- どの問題を「捨てる」かの判断
- 要求に沿った記述力(助言・分析の視点)
これは、どれだけ難解な簿記理論を理解していても身につきません。
では、何をすべきか?
簿記1級をやる代わりに、次のような実戦的トレーニングを徹底する方が圧倒的に効果的です。
✅ 1. 過去問を型で解く
- 財務指標の選び方は「定番パターン」で対応
- CVP分析・NPVは手順を体で覚える
- 手が止まる箇所は「仕訳」ではなく「割り切り力」
✅ 2. 80分完走シミュレーションを繰り返す
- 本試験は「時間との勝負」
- 正解率より、完答率が合否を分ける
✅ 3. 記述力を強化する
- 50字・80字で経営的判断を簡潔に書く練習
- 計算だけでなく「助言できる診断士」視点が問われる
🎓補足:簿記1級の勉強で身につく知識は限定的
簿記1級の出題範囲は膨大ですが、その中で事例IVに直接的に役立つのはごく一部です。
| 分野 | 内容 | 事例IVでの有用性 |
|---|---|---|
| 財務指標分析 | 流動比率など | ◎(そのまま使う) |
| CVP分析 | 損益分岐点、変動費率など | ◎(頻出) |
| 設備投資のNPV | 減価償却、税引後CF | ◎(実務レベル) |
| 標準原価計算 | 差異分析など | △(出題例ほぼなし) |
| 税効果会計・退職給付 | 制度的処理論点 | ×(出ない) |
| 連結会計・外貨換算 | 会計処理の応用論点 | ×(出ない) |
つまり、簿記1級の全範囲をマスターしても、事例IVに必要なのはせいぜい2割なのです。
✏️簿記1級では対応できない「事例IVの実際の設問例」
以下の設問は、簿記1級の知識だけでは対応できない、診断士試験・事例IV特有の思考力を問う問題です。
【令和元年度・第2問 設問3】
「売上高の変化を前提に、変動費率を逆算し、目標利益を達成するには?」
➡︎ CVP分析の応用であり、逆算型・条件付きの変動費調整問題。試験特有。
【令和2年度・第2問 設問2】
「広告の効果が出る/出ない確率を考慮し、それぞれのキャッシュフローの期待値からNPVを算定し最適案を選ぶ」
➡︎ 会計処理ではなく、リスク下の投資意思決定問題。
【令和5年度・第2問 設問2】
「X製品を中止すべきか。固定費の回避可能性と他製品への需要移動を考慮せよ」
➡︎ 単純な損益だけでなく、差額原価分析+戦略的視点が必要。
【令和6年度・第4問 設問1】
「事業部間取引における社内価格設定(全部原価+利潤)の問題点を80字以内で説明せよ」
➡︎ 財務処理ではなく、経営評価制度の妥当性を短文で助言させる問題。
✅まとめ:簿記1級で事例IV対策は“戦略的に非効率”
簿記1級の勉強には価値があります。ただし、
「診断士試験・事例IVに合格する」という目的に限れば、遠回りです。
合格に必要なのは、
- 経営者目線での判断力
- 時間制限下での解答戦略
- 助言できる力
つまり、「診断士として考え、書く力」こそが問われるのです。
最後に:あなたが目指すのは“診断士”です
「診断士試験に合格する」という目標のためには、
“診断士としての解き方”に特化した訓練がもっとも効果的です。
もし簿記1級をやりたくなったら、合格後のスキルアップとしてどうぞ。
でも今やるべきは、事例IVの過去問を、“経営の目線”で解けるようになることです。
